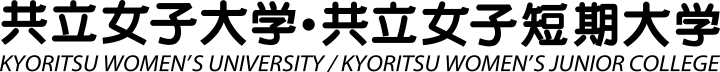文芸学部取り組み?プロジェクト紹介
更新日:2016年04月10日
フランス語?フランス文学専修
受験生へのメッセージ(武藤 剛史)
フランス文学を中心に探求する〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉
マルセル?プルーストの『失われた時を求めて』を熟読する
私は大学でフランス文学を学び、現在にいたるまで、フランス現代文学、とくにマルセル?プルーストを研究しています。プルーストは二十世紀小説の最高峰とされる『失われた時を求めて』という長大な小説の作者ですが、私はこの小説からじつに多くのことを学びました。人間とは何か、世界とは何か、あるいは「生きる」、「存在する」とはどういうことか、こうした人生の根本問題についての私の基本的考えは、ほとんどすべてプルーストに負っています。私がプルーストから学んだことは、ある意味で単純であり、つぎのように要約することができます。つまり、私たち人間は「生かされている」、〈いのち〉を与えられている、ということです。しかし、〈いのち〉を与えられるということは、同時に〈わたし〉を与えられることであり、さらには〈存在〉を与えられることです。〈いのち〉と〈わたし〉と〈存在〉は等記号で結ばれます。つまり、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉です。私たち人間は、絶えず〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉を与えられながら、ひとりの私、一個の主体として、この世界を生きているわけです。
〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉、それはけっして抽象的な概念ではありません。〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉は究極の現実、真のリアリティーであり、それに触れることは、何よりもまず、大きな喜び、このうえない歓喜、まさに至福なのです。〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉に触れた喜びを、プルーストはつぎのように表現しています。
「だが、口に含んだお菓子のかけらの混じった紅茶が口蓋に触れたその瞬間、自分のうちに何か異常なことが起こっていることに気づいて、私は身震いした。ある甘美な喜び、孤立した、原因の分からない喜びが、胸いっぱいに広がっていたのである。その喜びに浸されると、たちまちにして、人生の有為転変は取るに足らぬこととなり、人生の災難は無害なものとなり、人生の短さは錯覚としか思われなくなっていた。それはちょうど恋と同じような作用を及ぼして、私をある貴重な本質で満たしてくれたのだった。あるいはむしろ、その本質とは、私のなかにあるのではなく、私自身であった。もはや自分が、平凡で、偶然で、死すべき存在であるとは感じられなくなっていた。」

その他のフランス文学および日本文学の作家?作品
しかし、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉を探求し、それを表現しているのは、プルーストだけではありません。真に優れた文学作品は、それぞれに、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉を探求し、それを表現しているはずです。フランス文学で言えば、ボードレールやランボーなどの詩人たち、バルザック、スタンダール、もっと近いところではカミュやデュラスなどの小説家たち、二十世紀のいわゆるカトリック作家たち(モーリヤック、ベルナノス、ジュリアン?グリーン)、モンテーニュやパスカルやルソーなどの思想家たち、現代でいえば、イヴ?ボンヌフォワ、フィリップ?ジャコテ、ジャン?フォラン、ジャン?グロジャンなどの詩人たち、アンドレ?ドーテルの小説やクリスティアン?ボバンの散文作品なども、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉を、それぞれ独自に探求し、表現していると思います。日本でもよく知られている『星の王子さま』の中で、作者サン=テグジュペリは「たいせつなものは目に見えない」と言っていますが、それもまた、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉を指していると思います。
日本の文学では、古典では西行や芭蕉など、現代では宮沢賢治、保田與重郎、石牟礼道子、まど?みちおなどに関心を持っていますが、それもやはり、彼らもまた〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉を探求し、表現していると思われるからです。
美術?音楽
私が美術や音楽に興味を持つのも、同じ理由からです。美術では、オランダのレンブラント、フェルメール、ゴッホ、フランスではシャルダン、コロー、セザンヌ、ボナールなどに関心があります。また音楽では、バッハ、モーツァルト、シューベルトなどが好きで、モーツァルトやバッハについては、訳書もあります。バッハやモーツァルトを聴く喜びもまた、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉に触れる喜びにほかならないと思います。


哲学?宗教思想
哲学や宗教に興味を持つのも、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉を考えるうえで、大きな示唆を与えてくれるからです。哲学でいえば、さきにも挙げたパスカル、さらにさかのぼって中世キリスト教哲学のマイスター?エックハルト、トマス?アクィナス、現代ではカール?バルト、エティエンヌ?ジルソン、ジャン=リュック?マリオン、そしてミシェル?アンリなどの本をよく読んでおり、とくにミシェル?アンリの「いのちの現象学」に強い関心を持ち、彼の『キリストの言葉』を翻訳しています。
もちろん、聖書、とりわけ福音書をよく読みますが、同時に、仏教書にも親しんでいます。日本の仏教思想では、とくに道元、一遍、親鸞などに関心があります。たとえば、道元のつぎの言葉は、私たちを生かしている〈いのち〉と私たち自身の命との関係を的確に言い表していると思います。
「此生死は即ち仏のおいのちなり、これを厭ひ棄てんとすれば、即ち仏のおいのちを失はんとするなり、これに留りて生死に着すれば、これも仏のおいのちを失ふなり。〔…〕厭ふことなく、慕ふことなき、是時始めて仏のこころに入る。ただし心を以て計ることなかれ。言葉を以て言ふこと勿れ。ただ吾身をも心をも、放ちわすれて、仏のいへに投入れて、仏のかたよりおこなはれて、これに従ひもて行くとき、力をも入れず、心をも費やさずして、生死を離れ仏となる。」
現代では鈴木大拙、西田幾多郎、西谷啓治などをよく読みますが、それもやはり、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉への関心からです。ちなみに西田幾多郎は、『善の研究』の冒頭で、つぎのように言っています。
「経験するとは事実其儘に知るの意である。全く自己の細工を棄てて、事実に従うて知るのである。純粋というのは、普通に経験といっている者もその実は何らかの思想を交えているから、毫も思慮分別を加えない、真に経験其儘の状態をいうのである。たとえば、色を見、音を聞く刹那、未だこれが外物の作用であるとか、我がこれを感じているとかいうような考のないのみならず、この色、この音は何であるという判断すら加わらない前をいうのである。それで純粋経験は直接経験と同一である。自己の意識状態を直下に経験した時、未だ主もなく客もない、知識とその対象とが全く合一している。これが経験の最醇なる者である。」
以上で言われている「純粋経験」とは、まさしく〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉の経験にほかならず、プルーストがみずからの文学創造の源泉としている経験とまったく同じです。

受験生へのメッセージ
最初にも述べたように、〈いのち〉=〈わたし〉=〈存在〉の探求のきっかけとなったのは、学生時代に長い時間をかけてプルーストの『失われた時を求めて』を熟読したことです。皆さんもぜひ、大学時代に、そうした根本的な出会いをしてほしいと思います。大学を単なる「就職予備校」と考えるのは、まったく近視眼的であり、もったいない話です。職業を変えることはできますが、自分を取り換えることはできません。大学時代に人生の根本問題を考える基礎的能力――それは、自分を根本的に変える能力と言ってよいと思います――を養っておかなければ、そのあとではけっして身につくことなく、旧態依然たる自分のままで、「所詮この世は金と力だ」などと覚り切ったつもりになって、何かを真に経験するということもなく、真に他者と出会うこともなく、漫然と一生を送り、慌しいこの世の動きに押し流されていくほかないでしょう。