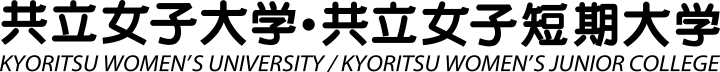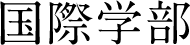Faculty of International Studies
国際学部取り組み?プロジェクト紹介 詳細
更新日:2018年10月29日
【国際学部】学生広報委員による取材記事(8) 「世界遺産が教えてくれること」
高麗なつみ (3年)
私はこれまで国際学部が主催する海外研究旅行に参加し、そこで観た世界遺産、例えば『リガの歴史地区』(ラトビア)や『アウシュヴィッツ=ビルケナウ強制収容所』(ポーランド)に興味を持ち、それについて詳しくなりたいと思い、勉強を始めました。世界遺産について学ぶと、その背景にある歴史的要因や文化的要因、政治的要因が見えてくるようになり、物事を関連付けながら、考える力を身につけることができると思います。今回は、そんな世界遺産に興味を持ってもらいたいと思い、世界遺産アカデミーの方々にご協力をいただき、記事を作成しました。
世界遺産アカデミーについて
世界遺産アカデミーとは、世界遺産検定の実施や世界遺産に関するセミナーや講演会を開催し、世界遺産への理解?保全活動の輪がより大きくなるよう活動している、特定非営利活動(NPO)法人です。
※世界遺産は、文化財、景観、自然など、人類が共有すべき「顕著な普遍的価値」(人類全体にとって、現在だけでなく将来世代にも共通した重要性をもつとされる価値)をもつ物件のことです。文化遺産?自然遺産?複合遺産の3つに分けられます。登録には、条件や基準があり簡単に登録されるわけではありません。現在(2018年8月現在)、167ヶ国1092件が登録されており、日本は22件?世界12位の保有国数です。ちなみに、1位はイタリアの54件です。
⇒世界遺産登録手順の流れ
Q1)世界遺産を観光しに行くときのポイントを教えてください。
世界遺産を観光するとき、いつも頭に入れておいてもらいたいのは、その世界遺産を大切にしている人がいるということです。都市や集落の世界遺産であれば、そこに暮らす人がいますし、信仰や歴史に関係するものであれば、それを自分達にとってかけがえのないものだと考える人がいます。また、自然であっても、その地の人々にとっては、何物にもかえがたい環境です。世界遺産というのは、「不動産」で観光する際にもそれだけを見てしまいがちですが、その背景には様々な人々がいて、守り伝えているということを思い出して、そうした人々にも目を向けると、観光の楽しさも理解も増します。
また、実際に世界遺産を訪れるというのは、本やテレビなどで見るよりも、ずっと貴重な経験となります。世界遺産に観光に行ったら、目や耳だけでなく、口や鼻、毛穴も全てをつかって、世界遺産を味わってきてください。世界遺産のある地域の陽射しや風、湿気など全てが、他所ではなく「その地域」にある世界遺産を作り上げている要素ですから。
Q2)私達が危機遺産保護のために少しでも力になれることは何でしょうか。
まず危機遺産に関心をもち、なぜ危機に直面しているのかを知ることです。そのためには、世界遺産としての価値や危機について学ぶ必要があります。また、危機というのは様々で、一つの国や地域だけでは解決できない問題もあります。今年(2018年)の世界遺産委員会で危機遺産リストに登録されたケニアの『トゥルカナ湖国立公園群』は、隣の国のエチオピアで行われたダム開発のために、環境や水質が変化してしまい、生態系の危機に陥ってしまいました。特定の世界遺産の危機だけを考えるのではなく、紛争問題も含めて地球規模で考えることが必要な危機も多くなっており、私達の日々の生活の中で気候変動対策に気をつけるなど、毎日、少し意識することが、世界遺産の危機を取り除くことにもつながります。
- 世界遺産検定
単に「資格を取る」ことが目的ではない、人類共通の財産?宝物である世界遺産についての知識?理解を深め、学んだ内容を社会へ還元することを目指した検定です。とは言うものの、資格を持っていると大学入試や就職に有利な場合もあるようです。下から順に4?3?2?1?マイスターと級が設定されています。
★私の行きたくなった世界遺産ランキング
私自身も世界遺産を受検し、現在もマイスターを目指し頑張っています。そうしたなかで、勉強して特に行きたくなった世界遺産を紹介します!
第一位:『屋久島』(日本)
東京23区ほどの広さの島に標高1,000メートルを超える山々が連なっており、標高が上がる毎に亜熱帯から亜寒帯まで植生が移り変わります。また、「月に35日雨が降る」と譬えられたほどの多雨地域です。有名なのは、「縄文杉」ですが、これは樹齢1000年を超えると言われています。朽ちることなく、1000年生き延びているという歴史や、日本で唯一の登録基準である「ひときわ優れた自然美の価値」を認められていることから、是非行ってみたいです。

『屋久島』(©Chris73,Wikipedia Commons,2008)
第二位:『メキシコ国立自治大学(UNAM)の中央大学都市キャンパス』(メキシコ合衆国)
このキャンパスは、メキシコ革命後の近代化運動の最中に建てられました。大学のデザインはメキシコの「壁画運動」とも関係があります。大学内には、映画館やスーパー、美術館、ラジオ局まで備え付けられています。同じ大学生として、想像を超えたキャンパスである上、このインパクトのあるデザインが、さらに大学の施設とは思えません。

『メキシコ国立自治大学』(© Lachaume, Wikipedia Commons, 2006)
第三位:『サナアの旧市街』(イエメン共和国)
この遺産はオススメというよりは、皆さんに現状を知って欲しい遺産の一つです。サナアはイエメンの首都で世界最古の都市とも言われ、中世アラビア都市の面影を色濃く残しています。旧市街で最も特徴づけているのが、6000棟もの高層住宅で、これらの高層住宅には鉄筋などは一切使われず、花こう岩や玄武岩でできた土台に、「アドベ」と呼ばれる日干しレンガを積み上げて作られています。
そんな美しい街が、イエメン国内の紛争により危機遺産に登録されています。私は吉竹広次(よしたけ?ひろつぐ)先生のゼミに所属していますが、ゼミ内でイエメンの現状のビデオを観たとき、絶句しました。人が住める場所とはとても言えず、怪我をした子どもや親を失った子どもが大勢いました。罪のない子ども達が大勢犠牲となってしまっていることに、心が痛くなります。また、衛生面からコレラが流行り大勢死者も出ています。このままだと、街が消えてしまいます。

サナアの街並み(© Chin tin tin, Wikipedia Commons, 2009)
★研究員?宮澤さんのおススメ世界遺産ランキング
第一位:『ヴェズレーの教会と丘』(フランス共和国)
ブルゴーニュ地方の丘の上にあるサント?マドレーヌ教会と小さな街が世界遺産に登録されています。ここはサンティアゴ?デ?コンポステーラへの巡礼路にもなっていて、昔から旅人を受け入れてきました。
サント?マドレーヌ教会の中には、古い十字架が何本も残されています。これは第二次世界大戦後の1946年に、ヴェズレーで平和を祈ることを呼びかけたときのもので、その中の1本は廃材で作られているのですが、それは、この平和の祈りに声がかからなかった敵国のドイツの兵士が自主的に参加したときにもってきたものです。ドイツ兵を受け入れた人々の和解と平和を感じることができる世界遺産です。

サント?マドレーヌ教会(© Vasill, Wikipedia Commons, 2008)
第二位:『テオティワカンの古代都市』(メキシコ合衆国)
アメリカ大陸最大規模の古代都市遺跡、テオティワカン。この都市を造ったテオティワカン人がここを捨て去った何百年もの後に、アステカ人がこの巨大都市を「発見」しました。
アステカ人は、この場所に神々が集い、月と太陽を創造したと考え、「神々の集う場所(テオティワカン)」と名づけました。彼らがここを、神々が造った都市だと考えたのも頷けます。現代のような、高層ビルが溢れている時代を生きる僕達でさえ、この都市の大きさには圧倒されるのですから、彼らの驚きはどれ程のものだったのでしょう。ぎらぎらと陽射しばかりが煩くて、誰ひとりいない静まり返った巨大都市。彼らは、驚きと畏怖の念、それに溢れんばかりの好奇心を携えて、恐る恐る足を踏み入れたに違いありません。まだまだ多くの謎に包まれているテオティワカンですが、これこそまさに、行って感じてみないとわからない圧倒されるような威圧感があります。現代に置き換えて考えてみると、ニューヨークから突然人がいなくなったようなものなので、考古学者でなくても好奇心が刺激されると思います。

『テオティワカンの古代遺跡』( © Jackhynes, Wikipedia Commons, 2006)
第三位:『広島平和記念碑(原爆ドーム)』(日本)
日本では「原爆ドーム」という名前で知られていますが、世界遺産名は「広島平和記念碑(原爆ドーム)」です。これは、世界遺産に登録されるにあたって、核爆弾の被害でなく、広島の人々の平和活動が評価されたため、その平和活動のシンボルとしての価値で、世界遺産になっているからです。実際に広島平和記念碑を訪れて、悪意によって捻じ曲げられた鉄骨や崩れるコンクリートを目の当たりにすると、戦争が人間の営みのうえで必要悪であるなんてコトは、僕には口が裂けても言えません。日本人は必ず一度、広島平和記念碑を訪れるべきだと思います。痛々しく凄惨で、誤解を恐れずに言えば、閑寂な美しさすら纏うその姿は、どんな反戦のスローガンよりも雄弁です。

『広島平和記念碑(原爆ドーム)』
番外編
皆さんも、ぜひ世界遺産に興味を持ってみてください。新しい発見があるかもしれません。そして、機会があれば実際に世界遺産の場所に足を運んでみてください。また、共立の皆さんには、そうした手段の一つとして、海外研究旅行もオススメです。観光だけではなく、教授による解説や企業訪問、現地の大学生とも交流をすることができ、濃密な時間を過ごすことができます。楽しみながら、2単位もらえますよ。
最後になりましたが、今回の取材にご協力くださったNPO法人世界遺産アカデミーの皆様に、この場を借りて、心から感謝申し上げます。