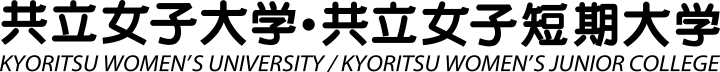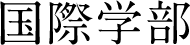Faculty of International Studies
国際学部取り組み?プロジェクト紹介 詳細
更新日:2019年04月24日
【国際学部】リレー?エッセイ2019(1)西山暁義「3つの国、3つの歴史? 三国博物館(ドイツ?レラハ)」
3つの国、3つの歴史? 三国博物館(ドイツ?レラハ)
西山 暁義
1.日本の「三県境」
私の生まれ故郷であり、現在も住んでいる小田原は神奈川の西端に位置し、箱根の山を越えるとそこは静岡県です。地理的には偏っていますが、戦国時代には関東地方の中心地(後北条氏)でもありました。しかし江戸時代になると、関東の端として西の外様大名に対する幕府の防衛ラインとなり、小田原藩は箱根の関所で「入り鉄砲に出女」を取り締まる役割を担うことになります。この関東地方の境界、入り口としての箱根、小田原というイメージは、幕府が滅び日本が近代国家となるなかで、関所がその意味を失った後も長く残ることになります。私事で恐縮ですが、私の父が1960年(第42回大会)に法政二高のメンバーとして夏の甲子園で優勝した際は、深紅の優勝旗が「箱根の山を越えた」(ただし3度目、戦後では2度目;春の選抜の紫紺の優勝旗の箱根越えは1957年(第29回大会)王貞治擁する早稲田実業の時)と言われ、凱旋列車が小田原駅に停車した際に、プラットホームで市長から表彰を受けたそうです。ちなみに母は大阪出身で、父が出場していた甲子園でアルバイトしていました。小田原と大阪というと、歴史的には戦国時代の怨念(豊臣秀吉の小田原征伐)がありますが、母が嫁いでくることは家族、親族的には問題にならなかったようです。
かくいう私の場合も、規模は小さくなりますが、妻の出身地とは戦国時代の歴史的な因縁がないわけではありません。妻の出身地は埼玉県北川辺町(現加須市)なのですが、渡良瀬川の向こう側の茨城県古河市は、文字通り古河公方の本拠地でした。自分で言うのもなんですが、妻とはケンカすることはほとんどないのです(*個人の感想です)が、唯一記憶に残っているのが、20年近く前の夏、里帰りで渋滞に巻き込まれた夜の車中、川越を通過中のことでした。これが、小田原の北条氏康が古河公方足利晴氏らを破った「河越夜戦」(1546年)の怨念が取り付いたせいだったのかは定かではありませんが、私たちの場合も、お互いの出身地が障害になることは全くありませんでした。
ところで境界というと、妻の実家から歩いてすぐのところに、最近テレビでも紹介された「三県境」というのがあります。埼玉、栃木、群馬の3つの県境が小さな溝で仕切られており、3歩で3つの県を行き来できる(手足を使えば同時に存在できる)、というものです。以前はやや傾いた、手作りの標識が寂しく立つだけだったのが(下写真左)、最近整備され(同右)、写メ撮影用のスタンドや、スタンプ付きの訪問証(下)まで設置されています。実際、今年の正月に里帰りした際散歩で立ち寄ってみると、何組かの訪問客が来ていました。また、ちょっと南に下り、渡良瀬遊水池を過ぎると、そこには「三国橋」という橋が架かっていますが、こちらは埼玉、栃木、茨城の三県の境付近であり、日本地図でこの付近を見ると、あたかも4つの県が接しているように見えます。
三県境の整備前(左)と整備後(右)
三県境「3歩で三県周回記念」証
とはいえ、県の向こう側にいったところで、言葉や通貨が変わるわけではなく、住んでいる人の考え方や感じ方が急に変わるわけでもありません。もしかしたら、最近映画化された『翔んで埼玉』が、埼玉の県境をめぐる関心を高め、それで三県境が一種「聖地」として注目を集めたのかもしれません。しかし、もちろんそれはフィクションであり、実際に(戊辰戦争での藩同士は別として)県同士で戦争したわけでも、県境を越えて難民が押し寄せたわけでもありません。
2.ヨーロッパの「三国境」:ライン川上流地域
島国の日本には「三県境」はあっても、地上の国境線は存在しません。一方、ヨーロッパ大陸には、日本の県境のように、多くの国境が存在し「三国境」も48地点存在するといいます。以前このHPでも報告しましたが、2年前に実施した海外研究旅行では、その1つであるナイセ川上流のドイツ?ポーランド?チェコの「三国境」を訪問しました(下写真)。このナイセ川とその支流(小川)で区切られた地点も、埼玉?群馬?栃木の「三県境」のように誰でも3歩で三国を回れるほど狭くはありませんが、幅跳びの選手であればもしかしたら可能かもしれません。「三県境」と比べてすぐに気が付くのは、ここにはそれぞれの国旗と真ん中にEUの旗が翻っていることです。三県境の訪問証には3つの隣接する自治体のマスコット(ゆるキャラ?)が描かれていますが、現地に県の旗や、ましてや日の丸が掲げられているわけではありません。また、三国境には各国の警察官が巡回する姿も見られましたが、三県境でそれぞれの県警が県境の警備にあたる姿を見たことはこれまで一度もありません。さらにいうと、EUの旗が象徴するように、2004年以降、三国はすべてEU加盟国になっていますが、公用語も通貨も異なります。
ナイセ川、ドイツ?ポーランド?チェコ国境(2018年3月ポーランド側で撮影)
このドイツ?ポーランド?チェコの「三国境」にも、歩行者?自転車専用の橋を造り、観光的に開発しようとする計画があるようですが、費用の問題もあり、今のところまだ実現していないようです。そもそも、現在の国境が三国の境界となったのは第二次世界大戦後のことであり、この「若い」国境線とそれをめぐる三国の波乱に満ちた歴史について、それを示唆する記念碑は点在しているものの、博物館のように集約的に教えてくれるような施設は存在していません。ただし、ドイツとポーランドの二国についていえば、ナイセ川をもう少し下流に下ったゲルリッツにある「シュレジエン博物館(Schlesisches Museum)」が、二国間の国境地域の歴史について興味深い展示を行っています(ここは、2011年の研修旅行の際に見学しました)。
一方、三国の歴史ということでいえば、3つの国に分かれた1つの地域の歴史を扱う博物館が、ドイツからみて反対側の南西の端、ドイツ?フランス?スイス国境に存在します。ここはライン川上流の、シュヴァルツヴァルト、ヴォージュ、ジュラの山々に囲まれた盆地の南部にあたります。この地方もまた、東の国境と同様、波乱に満ちた歴史を有していますが、異なるのは、その一国であるスイスが永世中立国の立場を守り続けたことであり、それはドイツとフランスの国境線が戦争のたびに頻繁に変わったのに対し、スイスの国境線は安定している、という点にも表れています。そしてまた、この地域は他の国境地域と比べ工業化が早くから進み、人口密度が高い(国境に隣接する市町村だけで現在約60万人が居住)のも特徴といえるでしょう。
スイス側のバーゼルに立つ三国境のモニュメント。左側がフランス、右側がドイツ。
三国国境地域の地図(グーグルマップから)。印は三国博物館の所在地。一つ上のモニュメントの写真の三国国境点はフランス側の町サン?ルイの地名の「イ」に当たる部分。
素朴に空想すれば、20世紀前半の2つの世界大戦のころ、ちょっと先の「国境線の向こう側」のスイスにスイス人として生まれていれば、従軍したり、占領されたり、食糧不足に悩んだりしないですんだのに、とわが身を恨んだフランス人やドイツ人も多かったのではないでしょうか。もちろん、実際にはスイスも自動的に中立が維持されたわけではなく、また中立国であっても、戦争の影響から免れなかったわけですが、私の好きな2つの戦争映画、第一次世界大戦を背景とする『大いなる幻影』(1937年)や、第二次世界大戦の『大脱走』(1963年)でも、ドイツ軍の捕虜となった主人公たちは、身の安全と自由を求めてスイスを目指し逃亡を図っています。さらにさかのぼれば、普仏戦争時(1870/71年)にブルバキ将軍率いるフランス東部方面軍がドイツ軍に追い詰められ、ブルバキ自身が自殺を図る(未遂)ほど絶望的な状況の中、交渉の末武装解除を条件にスイス入国を許可されたことが、設立されたばかりの国際赤十字(および戦時国際法)の最初の実践例として、「中立、人道的な平和の孤島スイス」というイメージを強めていくことになります。ちなみにこのブルバキ軍のスイス入国については、スイス中部のルツェルンに大パノラマが1881年に作成され、現在でも見ることができます。
『大いなる幻影』の最後の一場面。マレシャル中尉(ジャン?ギャバン)とローゼンタール中尉(マルセル?ダリオ)がスイスへと脱出すべく国境を越えようとし、成功する。
『大脱走』。オートバイに乗ってスイスへの国境線を突破しようとするヒルツ大尉(スティーブ?マックイーン)。
最後は鉄条網に阻まれ失敗。ちなみにこのシーンはスイスではなく、オーストリアとの国境近くのドイツの村で撮影された。
いつものように前置きが長くなってしまいましたが、ここから三国博物館(Dreiländermuseum / Musée des trois pays)について紹介していきたいと思います。博物館があるのはドイツで、上の地図にもあるように、スイスのバーゼル市とは地続きであるレラハ(Lörrach)という町にあります。
この博物館の起源は1882年に遡ります。この年は、レラハが1682年に領主から都市としての権利を認められてから200周年にあたり、その記念行事の一環として、町の歴史的な事物が展示されました。そして同じ年に郷土史協会Altertumsvereinも結成されることになります。町の市民たちがこれに参加し、第一次大戦前夜の1912年には町の高校(ギムナジウム)の一室に展示ルームを確保することができましたが、開戦によって中断することになります。正式に博物館が、この時期ドイツ各地に見られる「郷土博物館Heimatmuseum」の名称の下建設されたのは、1929年の世界恐慌の混乱がなお続く、1932年のことでした。経済的な困難にもかかわらず博物館が開設されたことは、それだけ「おらが町」や地域(レラハの場合は「バーデン辺境伯領Markgräferland」)のアイデンティティを守ろうとする市民層の熱意を示すものであり、彼らから多くの寄付や寄贈が行われました。現在、博物館が所蔵する展示品は5万点にも及ぶそうですが、その多くが市民たちの寄贈によるものといいます。
その後ナチの時代、第二次世界大戦を経て、西ドイツの時代の流れのなかで、さまざまな紆余曲折がありますが、ここでは省略します。1978年に現在の場所に移った博物館は、その場所の名から「ブルクホフ博物館」に改称しましたが、それがさらに現在の「三国博物館」となるのは2012年、今から7年前のことでした。しかし、その流れはすでに20年以上前から始まっていたといいます。というのも、終戦50周年の1995年には、スイスのリースタールの(バーゼル?ラント)州博物館、フランス?アルザス地方のミュールーズ歴史博物館と共同で、第二次世界大戦直後の歴史を展示する「戦後Nach dem Krieg / Après la guerre」が開催され、パンフレットも共同制作されました。さらにその三年後には、1848年革命の150周年ということで、ライン上流地域における革命の展示が続き、たんなるドイツの「おらが町」の歴史や文化だけではなく、国境を越えた地域の歴史と文化の展示が行われるようになりました。こうした三国国境地域の博物館同士の協力、交流は、2002年に「トリレナTrirhena」(三国からなるライン川上流圏)の常設展示の実現に結実しました。そしてその後のさらなるネットワークの拡大や共同プロジェクトにもとづく特別展が行われるようになり(ただし、同一の展示を行うということではなく、定期的に1つのテーマについて―たとえば、カーニバル、宗教、戦争?平和など―各博物館がそれぞれ個性を活かした展示を行いつつ、連携するもの)、こうしたネットワークの中核の博物館として2012年に「三国博物館」に改称されることになりました。
(左)三国博物館の入り口、(右)玄関に貼られたEUの地域間協力振興プログラムInterregの助成を受けていることを示すプレート
4.いくつかの展示の紹介
このような博物館の新たな方向性を打ち出し、推進してきたのが、1991年から現在に至るまで館長を務めているマルクス?メーリンクさんです。メーリンクさんは大学で歴史学と民俗学を学んだ後、博物館での活動を志し、アメリカのデトロイトにあるヘンリー?フォード博物館などで実習を経験し、その後ドイツの他の博物館の設立に携わった後、故郷のレラハに戻ってきました。着任後、国境を越える連携以外にも、レラハに住むトルコ人移民や、統一後多く移り住むようになったロシア系ドイツ人や再建されたユダヤ人コミュニティーの歴史と現在にかんする展示など、地域の文化遺産だけではなく、統一後多文化化が加速するレラハの社会を取り上げた特別展も実施しています。
三国博物館は2016年に一度訪れているのですが、昨年10月に再訪した際にはメーリンクさんにお会いし、インタビューをすることができました。すでに上に書いた内容もそれにもとづくものですが、以下では彼の案内の下で観覧した常設展のいくつかを紹介したいと思います。
常設展示の最初のスペースは、ライン川上流の環境、生態系そして考古学的な内容についてです。もちろんその頃は3つの国家が存在していたわけではなく、また現在でも環境や生態系は国境線で変わるわけではありません。そうした同じ空間のなかで生活しているという意識を与えようとするものになっています。
(左)ライン川上流圏の航空写真、(右)主に19世紀に進められた、蛇行するライン川の直線化についての模型。現在では生物、環境保全の観点から、沿岸の池沼にはビオトープが設けられるようになっている。
近代以降、ドイツ、フランス、スイスがそれぞれ国民国家となっていく過程については、まずそれぞれの国のステレオタイプとなっているオブジェが置かれており、身に付けることもできます。そのあと、それぞれの国において、「国民」としての意識が―しばしば相手を敵とみなしながら―どのように作られていったのか、について、スペース、そして視覚的にも区別した形で展示されています。
フランス人のステレオタイプ、ベレー帽を被り、バゲットを持つメーリンクさん
モザイク状の領地に分かれていた近世から(左)、三国へと収斂していく様子(右)を示した地図。ボタンを押すと、パズルのピースが脱落し、3国の地図が現れる仕掛け。
しかし、第一次世界大戦までの時期(1871~1918年までは、現在フランス領のアルザスもドイツ帝国の一部でした)、ドイツとスイスの国境では、モノの輸送については税関での検査がありましたが、ヒトの移動はほとんどフリーパスであったといいます。実際、平日数千人のスイス人たちがドイツの工場で働きにやってくるのも、逆に週末ドイツ側から余暇を楽しみにバーゼルへと出かけたりするのも、日常の光景でした。しかし、1914年の大戦の勃発は、こうした国境の開放性に終止符を打つことになります。これ以降、ヒトの国境横断も厳しく監督されるようになり、この地域にはさまざまな種類の身分証明書が発行されることになります。博物館に展示されている多種多様な身分証明書は、まさに緊張に満ちた20世紀前半のこの地域、そしてヨーロッパの歴史を象徴するものといえるでしょう。と同時に、こうした取り締まりの裏には、必ず「密貿易」が存在します。ある意味地域の経済を成り立たせていたともいえるこの「必要悪」についても、押収されたジーンズなど、さまざまな展示物が、国境の理念と現実の落差について語っています。
大戦時の国境通過地点の様子。この時にヒトの通行もチェックされるようになった。物資の輸送の検査は1880年以降、左側の税関において行われていた。(*)
ライン川上流地域において発行、使用された身分証明書の展示(の一部)(*)
税関において押収された「密貿易品」(の一部)(*)
また、第二次世界大戦期についての展示でも、ドイツ、フランス、スイスでそれぞれ反ナチの抵抗運動にかかわった人物や家族が展示されており、こうした「三国視点」は展示全体を貫いています。掉尾を飾る最上階のスペースでは、この地域に住むさまざまな出自の人たちが、自分たちの生活や他国に対する印象を語る音声を聞くことができます。
「抵抗者:3つの運命」ドイツ、スイス、フランスでそれぞれ反ナチ運動に関与した人の例が紹介されている
(ここにもあるように、解説の文章は、独仏二か国語で同じ大きさで書かれている)。
かつてフランスの歴史家リュシアン?フェーブルは、「国境を大地のなかに『埋め込む』のは警察官でも税関の役人でもなく、また要塞の壁に据えられた大砲でもない。それは感情、高揚した情熱、そして憎悪なのである」と述べました。それは、まさにドイツとフランスの間の感情、憎悪が高まっていた1935年、『ライン川』という本のなかに書かれた一節です。三国博物館は、自国だけではなく、「すぐ向こう側」の国や人びとの歴史や文化、視点を取り上げることで、この相互の感情の歴史について理解が深まるとともに、お互いの社会が独立して存在しているのではなく、相互の関係のなかで作られ、変わってきたこと、ただしそうした事実自体、そこに住んでいるということだけで認識できるわけではないことも教えてくれる、貴重な場所であると感じました。国立や州立の立派な博物館ではなく、日本では全く無名ですが、もしこの地域を訪れる機会があれば、ぜひ立ち寄ってみてもらえればと思います。
三国博物館HP (ドイツ語版)
おわりに(謝辞)
この記事の作成にあたっては、三国博物館館長のメーリンクさん、そして学芸員のヴァルトラウト?フプファーさんに大変お世話になりました(掲載写真のうち(*)が付いているのは、博物館から提供していただいたものです)。記してお礼申し上げます。
* Zum Schreiben dieses Artikels habe ich eine großzügige Unterstützung von Herrn Markus Möhring, Direktor des Dreiländermuseums, und Frau Dr. Waltraud Hupfer, wissenschaftliche Mitarbeiterin, erhalten. Ihnen beiden sei hier herzlich gedankt. Die mit (*) markierten Fotos wurden vom Museum aufgenommen und mir angeboten.
とくにメーリンクさんには、博物館でのインタビューや案内にとどまらず、夕食まで招待していただきました。その場所はブドウ畑の丘に立つ「三国展望」という名のレストランとまさに「三国尽くし」で、文字通りライン川の向こうのスイス、フランスを望み、フランス側にある三国共同の「ユーロ空港」から飛行機が飛び立つのも見ることができました。
レストラン「三国展望Dreiländerblick」とそこからの夕景(真ん中を水平に走る黒い線がライン川=国境)