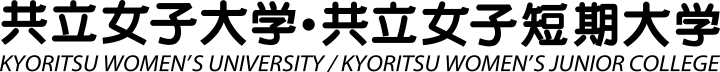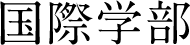Faculty of International Studies
国際学部ニュース詳細
更新日:2021年09月21日
その他
【国際学部】リレーエッセイ(2)菅野敦志「オリンピック?台湾研究?“国際”」
オリンピック?台湾研究?“国際”
菅野 敦志
2013年に東京でオリンピックが開催されるというニュースを聞いたとき、「すごい、生きている間に日本でまた夏季オリンピックが開催されるなんて」と、言い表せない感動と嬉しさが心の底から沸き上がったことを覚えている。そして、せっかく東京オリンピックが開催されるのだから、自分にも何かできることはないかと考えた結果、アジアとオリンピックについて調べてみようと思いついた。
1940年の開催が決定していたにもかかわらず、日中戦争のために返上されてしまった「幻の東京オリンピック」については、関連科目の授業の中でも概略程度は紹介するようにはしていた。テレビの報道などを観てその事実をすでに知っている学生も、少数ではあったがいたようであった。だが、実際のところ、私自身はその内実についてそれほど詳細に把握していたわけではなかった。戦後、アジアで初めてとなる東京オリンピックは1964年に開催された。だが、私は1975年生まれのため、生まれる11年前のスポーツイベントについての知識と理解は、正直言って非常に乏しいままであった。そうして、私は「2020東京オリンピック」を契機として、新たな領域に足を踏み入れることにした。けれども、忙しさにかまけて、実際に手を付け始めたのは、思い立ってから数年が過ぎた後のことであった。
思い起こせば、オリンピックは私が“国際”に目を向けるうえで実に多大な影響を与え続けてきた。個人的には、1984年のロサンゼルスオリンピックや、1988年のソウルオリンピックの印象が強烈に残っている。前者は小学4年生で、カール?ルイスの活躍に胸が震えた。後者は中学2年生のときだったが、フローレンス?ジョイナーがきらびやかなネイルを前後させながら美しく疾走する姿に、日本の女性アスリートとは異なる個性とその表現方法を目の当たりにし、アメリカという国が象徴していた自由と強烈な個人主義への憧れをより強くさせた。オリンピックは“世界”という存在を身近に感じさせてくれ、自身が進学や進路決定において“国際”を追い求めるうえでも、大きく背中を後押ししてくれたように思う。その一方で、ソウルオリンピックを妨害するために北朝鮮の工作員が起こしたテロ事件、いわゆる「大韓航空爆破事件」は実に衝撃的であった。オリンピックという「平和の祭典」が、実際には国家同士の対立や抗争にも巻き込まれる、あるいは利用されるリスクを抱えるイベントでもある、ということにも気付かせてくれた。
話を元に戻したい。私は台湾研究を専門としている。そのため、アジアとオリンピックについて調べてみようと思ったとき、台湾研究という専門の立場から問題意識を狭めてみることとした。そうして考えてみると、そもそも1940年の「幻の東京オリンピック」と1964年の東京オリンピックのときにはどのような台湾人選手がいたのか、という疑問が浮かんだ。調べてみると、後者の1964年の東京オリンピックでは、「アジアの鉄人」と呼ばれた楊伝広(1960年ローマオリンピック十種競技銀メダリスト)を始めとする選手たちに関する文献を多く見つけることができた。その一方で、簡単ではなかったのは前者の1940年「幻の東京オリンピック」の方であった。日本統治下の「外地」(日本統治下にあった台湾、朝鮮半島、満州など)の選手には、日本代表となった朝鮮出身のオリンピアンのなかに孫基禎や南昇龍といったメダリストが存在していた。これらの朝鮮半島出身の選手たちについては、札幌大学の金誠先生の研究を参照されたいが(金誠『孫基禎―帝国日本の朝鮮人メダリスト』中央公論新社、2020年。金誠『近代日本?朝鮮とスポーツ―支配と抵抗、そして協力へ』塙書房、2017年)、その一方で、台湾出身のオリンピアンも存在はしていたものの、残念ながらメダリストとなる選手はいなかった。ただ、張星賢という台湾人初のオリンピック選手は2008年の北京オリンピックを契機として台湾でも再び注目を集めるようになっており、彼に関する文献は比較的多く見つけることができた。
けれども、日本統治下の台湾で発行されていた新聞や、戦前の日本の陸上雑誌を調べていくと、詳細が不明な選手も少なからずいた。最も気になったのは、カサウブラウやラケナモといった、台湾の先住民族のなかでもアミ族の選手たちの存在であった。二人とも、5千メートルや1万メートルといった中長距離の選手であった。どうやら、もし1940年の東京オリンピックが開催されていたなら、活躍の機会が得られたかもしれない選手たちのようだった。しかしながら、彼らが戦後も競技を続けていたのか、どのような人生を歩んだのかについて、まったくもって手がかりを得ることができなかった。台湾側の研究者による研究を参照しても、彼らに関しては名前以外の情報を得ることができなかった。そもそも、彼らが先の大戦を生き延びることができたのか、もし生き延びたとしても、戦後どのような中国名となって生き続けたのか、知る由もなかった。
話が長くなってしまうので経過に関する説明については割愛するが、最終的に私は幸運にもそれらの先住民陸上選手たちのご遺族と出会うことができ、彼らがたどった人生について知り得た内容を論稿にまとめることができた。オリンピックという国際スポーツイベントから生まれた興味が、台湾の地域研究という、国境を越えて実践される学問を通じて実を結んだ。それは、ひとつの“国際”の果実として世に送り出されたようにも思えた。
台湾人選手たちは、戦前は日本代表として、戦後は中華民国代表として、そして中華人民共和国が世界各国から唯一の中国として承認されるようになってからは、「チャイニーズタイペイ、中華台北」の名義でもってオリンピックに出場することとなった。1964年の東京オリンピックでメダリストとなった楊伝広にしても、日本統治下に生まれ、戦後に中華民国籍となった先住民族選手(アミ族)であった。4年に一度開催されるオリンピックという横軸だけに注目した場合には「ひとつの国家に属する一選手」としか認識できなくても、その選手の人生を縦軸として見た場合には、けっして「○国人選手」という単純化された理解に落とし込むことのできない複雑さを併せ持っていた――そのような気づきも与えられた。
オリンピックは国際的なスポーツの祭典であるが、異なる国家の選手たちが競い合うという表面的な国際性に目を奪われ、自国の選手の活躍に執着して応援するような祭典として楽しんでしまっていたかつての自分と、そうした以前の自分が気づかなかった奥深さを、今さらながらようやく理解することができたように思えた。本来目を向けるべきであったのは、国や肌の色を問わず、さまざまな国家のあいだに身を置くことを余儀なくされ、そうした狭間にありながらも懸命に生き抜いた人々の存在であったのではないか。個々の主体としてのアスリートを、ある国家の代表として単純視するのではなく、あくまで一人の人間として理解し、共感を覚えるためにも必要とされていたのが“国際”という“あいだの視座”だったのではないか、と。その点では、近年の日本でも多様な背景を持つ選手が増加しているし、このことをとても嬉しく感じる。
東京オリンピックの開催は、私に新たな研究の扉を開かせてくれた。もし東京オリンピックが開催されなかったら、私はスポーツ史研究には足を踏み入れていなかっただろうし、素敵な研究仲間との出会いもなかっただろう。本来東京オリンピックが開催されるはずだった2020年には、同研究グループで選手や人物に焦点を当てた研究成果を出すこともできた(高嶋航?金誠編『帝国日本と越境するアスリート』塙書房、2020年)。その意味において、私にとってオリンピックは特別な存在となった。もちろん、グローバルなパンデミックの下、困難な状況に置かれ続けたことからもオリンピック開催をめぐる賛否両論は数多く見られたが、歴史を振り返ると、1920年のアントワープオリンピックも、1918年から続いたスペイン風邪のパンデミックが依然として影を落とし続けるなかで開催された大会であった。
この春、私は10年過ごした沖縄を離れて東京に戻り、共立女子大学国際学部に着任した。緊急事態宣言が解除された後の6月26日には、入場制限に従って三密を避け、万全の感染防止対策を施したうえで、神宮外苑にある日本オリンピックミュージアムにて1年生必修科目「基礎ゼミナール」の学外研修を行った。
オリンピックが国境を越え人々の心を結びつける平和の祭典であるならば、同時に、パンデミックも国境を越えて押し寄せる試練の荒波の一つであったといえよう。実に、“国際”とは必ずしも憧憬や共感といった感情を投影させるだけで済むような対象ではなく、ときにはわれわれが居住するところの共同体に対する危機を外からもたらしうる脅威として見られる向きもあるだろう。それでも、「われわれと他者」といった固定化された二分法から距離を置いて物事を見続けるためにも、“国際”という視座から得られる気づきを大事にしていきたい。そして、“国際”という視座から、まだ見えない未来への示唆と希望についても学び続け、追究し続けていきたいと思う。