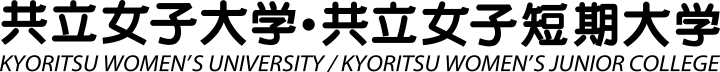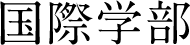Faculty of International Studies
国際学部ニュース詳細
更新日:2025年09月26日
学生の活動
【国際学部】日本語教師養成課程「日本語教育実習」履修生が日本語学校で教育実習に参加しました。
2025年8月19日から22日まで、「日本語教育実習」履修生10名(以下実習生)が、押上にある東京富士語学院で教育実習に参加しました。4日間の教育実習は「授業見学、学習者との対話実習、そしてチームティーチングでの教壇実習」と密度濃いプログラムで行われました。8月の実習に先立ち、6月下旬には実習生は、同校の実習クラスで、授業見学のほか、後述する「対話実習」を経験しました。
東京富士語学院での教育実習は、昨年に続いて二度目です。今年は8月の実習までに、同校の学習者及び先生と何回か交流する機会を持つことができました。6月には、教務主任の倉八順子先生(教育学博士)にゲスト講師としてご出講いただき、「対話的であること」の重要性についてお話しいただきました。7月24日には、「日本語教育実習」授業に、倉八先生が同校のインターンシップの学生2名とともに再度おいでになり、実習生の発表を見学し、コメントしてくださいました。7月31日には、同校の社会見学活動の一環として、実習クラスの学生20名が倉八先生、クラス担任の石川正治先生とともに本校見学に来訪しました。共立講堂や本館の屋上、国際学部のフロア、図書館などの見学の案内を実習生が引き受け、学習者とも交流しながら回りました。実習生は学習者と友好的な関係を深め、8月の実習を迎えることができました。
.jpg)
.jpg)
8月の教壇実習は、10名が3つのグループに分かれ、チームティーチングでCLIL(Content Language Integration Learning:内容言語統合型学習)の実践に取り組みました。実習生はそれぞれグループで選定したトピック「日本の清掃文化」「就職活動前の自己分析」「スマホ認知症」に関して、資料を基に教材を作成し、教案を検討するなど、夏休み中も準備を進めました。当日はどのグループも、グループ内での分担の確認し、努力の成果を示す授業を行うことができました。
.png)
.png)
.png)
.jpg)
「対話実習」とは、実習生1人ないし2人が、数名の学習者のグループに入り、20分~30分程度のまとまった時間、選んだテーマについて話すことによって、その機会が日本語を用いた対話の場になるように進行するという活動です。「対話」は、倉八先生の実践のキーワードであり、ご著書では「「対話」とは、他者性(他者が自分とはまったく異質な存在であること)を前提としたコミュニケーションの営みです。「対話」は同質性を前提としたコミュニケーションである「会話」とは異なります」(倉八順子(2021:18)『「日本語教師」という仕事:多文化と対話する「ことば」を育む』)と説明されています。対話実習では実習生は「伝達ではなく、会話ではなく、〈対話〉を目指して」(倉八順子(2025:144)『対話による日本語教育:国家資格「登録日本語教員」を目指して』)学習者とやり取りをする実践に取り組みました。
6月の第1回目の対話実習では、難しかったという声が実習生から多く聞かれました。そこから実習生は「対話とは何か」を考え、8月の実習には資料の準備もして臨みました。その結果、前回より対話を深めることを意識したやり取りができたという声が全員から聞かれました。
後日、倉八先生から評価表とともに、実習クラスの学習者のお礼状と作文をいただきました。実習生にとって何よりのプレゼントとなりました。
〔実習生最終レポートより〕
●今期の教育実習でどんなことを学んだか、そしてその学びをどう今後の人生に活かすか
* 今回の教育実習を通して最も印象に残ったことは、「学習者一人ひとりが異なる背景や考え方を持っており、その多様性を尊重することが何より大切だ」という点である。教壇実習でも対話実習でも、学習者の国籍や年齢、経験の違いによって反応や発言の仕方が大きく異なり、ときには意見が偏ったり、思わぬ方向に話題が展開したりする場面もあった。しかし、それこそが実習の中で得られた貴重な学びであり、私自身「正解はひとつではなく、人の数だけ考え方や感じ方がある」ということを実感する機会となった。
また、授業を進めるうえで、相手の語彙や知識に合わせて言葉を選ぶこと、一方的に説明するのではなく、待つ姿勢を持って学習者自身の考えを引き出すことの重要性にも気づかされた。これは教員としてだけでなく、今後社会に出て働くときにも役立つ姿勢だと思う。就職した際には、同僚や顧客など、多様な価値観や考え方を持つ人々と協働する場面が必ずある。そのときに、自分の意見を一方的に押しつけるのではなく、相手の立場を理解しようとする姿勢を持つこと、そして異なる考えを受け入れながら対話を続けていくことが、信頼関係を築くうえで不可欠だと感じている。
実習は“教える側に立つ経験“ではあったが、実際には学習者とのやり取りを通して私自身が学びを深める時間でもあった。この経験を糧に、教員という進路に進むかどうかにかかわらず、将来どのような職場環境に身を置いても、多様性を尊重し、相手と誠実に向き合える人間でありたいと思う。(H.O)
* 人と直接関わり、コミュニケーションを取る適切な方法を学ぶことができたと思います。実習準備のなかで行ったグループのメンバーとの協働、そして対話実習のなかで行った相手と向き合って話すこと、また教壇実習で行った人の前に立って伝えることなど、多様な場面で、人と多様な関わり方をすることができました。私は卒業後、エアラインのグランドスタッフとして空港で働きます。接客のお仕事なので、やはり人と直接コミュニケーションを取ることが多いです。そのため、今期の授業、そして実習で取り組んできた、人と直接コミュニケーションを取ることが必ず役に立つと思います。特に、空港では多様な方、様々な国籍の方と関わる場面が多いです。ゆえに、日本語学校で日本以外の方々と関われたことは私にとって貴重な経験になりました。対話実習、そして教壇実習で意見を述べてもらう際に、国によって、人によって本当に様々な考え方があることを肌で感じました。この多様性を認識できたことを今後のキャリアで生かしていきたいです。(M.M)
* 人との関わり方、相手に伝える話し方からグループとして何かに取り組むときの姿勢まで本当に様々なことを学びました。相手に合わせてどのような声のトーンでどんな言葉を使って話せば伝わるか、相手に果たして本当に伝わっているのかを常に意識しながら人と過ごすという機会はあまりなかったので、今回凄く意識的に自分の話し方や周りの見方を考え直す機会になりました。今後、人と関わることが多くなっていくと思うし、就職先が海外のかたとも関わる可能性が高いところなので、今回学んだ相手に合わせたコミュニケーションをより普段から意識して実践していけたら良いなと思います。また、将来的に日本の学校現場の外国籍児童の支援をしたいので、その目標に向かって今回のことを忘れないよう日本語教育にボランティアなどでも携わっていければと思っています。(M.I)
* 日本語教育実習は思っていたよりも大変で、それでも強い達成感を感じる経験となった。普段一人でいることが多い自分にとって、他者と関わり、時に意見がぶつかり合いながらなにかを作り上げる経験に難しさを感じることもあったが、それは社会に出ればいずれ経験していくことであり、今回の実習を通してこのような経験ができてよかった。また、東京富士語学院の倉八先生、2-2クラスのみなさんにも実習生として温かく迎えていただき、これからも日本語教育について学び、これからの人生でいずれは日本語教育に関わっていきたいという気持ちが芽生えた。(H.N)
教育実習生を受け入れていただきました東京富士語学院と倉八順子先生には深く感謝申し上げます。また、日本語教育実習を実施するにあたり、サポートいただきました辻山国際学部長、佐藤雄一先生、ほか助手の方々にこの場をお借りしてお礼申し上げます。
(授業担当教員:菅生早千江(短大文科))