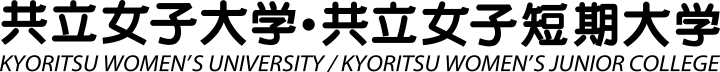卒業生インタビュー

看護の仕事は患者に真摯に向き合い、その積み重ねが実を結ぶ。

看護学部 看護学科(2017年度卒業)
勤務先:東京大学医学部附属病院 看護師
Q1 現在のお勤め先?職業を目指したきっかけや理由を教えてください。
幼少期から漠然と看護師に対する憧れがありました。それが将来就きたい職業として明確になったのは、高校での進路選択の際に人と関わる仕事がしたいと思ったこと、同時期にがんを患った祖父の入院が重なり、看護師という職業を間近で見て感じることができたことがきっかけでした。現在の勤務先への就職を決めたのは、学生時代にどのような種別の病院に勤めるかを決めかねていたところ、インターンシップで5~6軒の病院を見学し、その中で東京大学医学部附属病院(以下、東大病院)に勤務する看護師の、患者さんに対する誠実で真摯に向き合う姿勢と専門性を活かして働く姿に感銘を受けたこと、大学病院だからこその教育体制が充実し確立されているところに惹かれたことが理由です。

Q2 お仕事の具体的な業務内容を教えてください。
循環器内科病棟で入院患者さんを対象に看護に従事しています。ここでは、慢性心不全から心筋梗塞や不整脈でのカテーテル治療まで多岐に渡る治療患者さんがいます。カテーテルの治療は侵襲的治療のため合併症に、慢性期の患者さんは薬剤投与中の変化に注意して観察しています。生活の援助だけではなく、循環器内科の患者さんなので常にモニターには緊張感を持って観察しています。また退院後の患者さんがご自宅で過ごせるようにリハビリテーションや家族への支援、地域包括センターや区役所の職員と打ち合わせをすることもあります。循環器病棟ならではの仕事としては、心不全での再入院を少しでも減らせるよう指導を行っています。現在、私は主に心不全の再入院防止のためのパンフレット作成?改定と部署でのACP(Advance Care Planning)実践の普及に取り組んでいます。患者さんの症状に合わせた心不全指導にも取り組みたいと思ったことから、心不全療養指導士の資格も取得しました。看護師歴も7年に達し、病棟全体をまとめるリーダーを務めたり、新人教育に携わったりしています。
Q3 やりがいを感じたお仕事でのエピソードを聞かせてください。

長期に渡る入院でさまざまな治療や薬剤の副作用が出現していた若年の男性の患者さんがいらっしゃいました。現れた症状に対し私は常に対応し、コミュニケ―ションを大切にして患者さんに関わっていました。3ヶ月ほどの入院期間は患者さんにとってとても大変で、想像を絶するほどのつらい時間だったと思います。入院期間中は気丈に振舞われていたその患者さんが退院する際、涙を流しながら「渡久平さんがいたから頑張れました」と仰ってくださったときは「頑張ってよかったな」と思いました。最近では、意識レベルが優れず常に昏睡状態だった患者さんの担当になり、日々の状態に注視しながら徐々に患者さんの意識が回復していく過程でリハビリテーションに積極的に取り組み、ACPを実践し、患者さんから「自宅に帰りたい」という希望を聞き出し、最終的には自力歩行により自宅に帰れるようにできたことは、この先も忘れられない事例だと思います。思うようにいかないこともたくさんありますが、看護の仕事はいかに自分が患者さんと真摯に向き合うかが大事で、その積み重ねが実を結ぶと考えています。看護の力で患者さんが持つ力を引き出し回復まで導くことができる、看護は可能性を秘めていると仕事を通して実感できました。そんな私の誇りは、数年前に東大病院のスタッフ表彰でベストスタッフに選出されたことです!!
Q4 共立女子大学での学びは、今のお仕事にどのように生かされているかを具体的に教えてください。
共立女子大学で学んだことはたくさんあります。入学直後の基礎領域から始まり、年次が上がるに連れて専門領域での学ぶことが増えてきます。全てを覚えているわけではありませんが、仕事として実践する中で「そういえば大学で学んだな」と思うことがたくさんあります。看護実習では患者さんと関わり、学んだことがやはり活きていると思います。またカンファレンスで自分の意見を述べ、他者の意見に耳を傾け、最良の方法を導くというプロセスは、実習で何度も繰り返し経験したことで鍛錬されました。これは看護の仕事においてとても大切な姿勢です。ゼミでは苦労して論文を読み解き、分からないことは調べ、自分自身で論文を仕上げました。その貴重な経験とついた習慣は社会人になってからも自ら調べる、学ぶという今の私の姿勢を培った出来事であると思います。また、また、実習時に先生から「家族だったらどうする?」と言われたことは、患者さんに対して、また違った視点で話すことができると思うので、実習の時にもらった言葉は今でも大事にしています。
Q5 今後の夢や目標は何でしょうか。
私自身、自分の進路に迷っています。元々は地域で働くことを目標としていましたが、病院で看護職として働くこともとても楽しく、これをもっと続けたいとも思っています。その他には大学院に進学し、専門性を深めたいと考えています。
Q6 共立女子大学への入学、受験を検討している受験生に向けてメッセージをお願いします。
共立女子大学は学ぶための環境が整っていると思います。なにより先生方のサポートが手厚いところが魅力だと思います。演習が多いことも特徴で、看護師の毎日の業務でも基礎を忠実に守ることが大切で演習を受けたことが活きています。就職してからも練習ができる機会はありますが、学生時代に基礎を学ぶことで安心して働けることに繋がると考えます。
(2024年3月掲載)